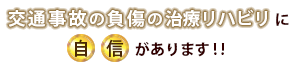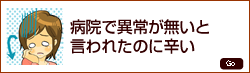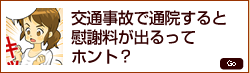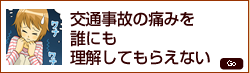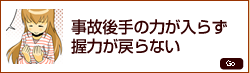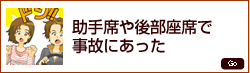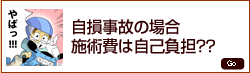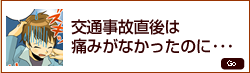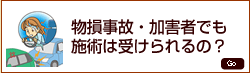2022年08月26日
万が一交通事故に遭ってしまった場合、
どうすれば良いのか?
どこへ連絡する必要があるのか?
その順序をご説明します。
①119番へ連絡
負傷者の確認後、応急処置をして救急車の手配をしてください。
②110番へ連絡
軽い事故でも必ず連絡してください。
怠ると負担金が増える場合や、法律で期せられる場合があります。
➂お互いの連絡先の確認
相手の氏名・住所・連絡先などを記録してください。
④任意保険会社へ連絡
その場での示談は禁物です。
ご契約されている任意保険会社へ連絡してください。
⑤治療へ
当院へご連絡ください。
患者様の完治までお手伝いしいます。
<りゅうた整骨院公式ホームページ>
宝塚市のりゅうた整骨院
<宝塚市の交通事故治療・むち打ち治療情報サイト>
宝塚市交通事故治療・むち打ち治療.com|整形外科連携の整骨院
<おかげ様で宝塚市口コミ上位!>
WEB上の患者様の口コミはコチラ
<鍼やお灸に関する口コミ上位!>
りゅうた整骨院公式しんきゅうコンパスページ
<りゅうた整骨院のフェイスブックページはコチラ>
りゅうた整骨院公式facebookページ
<りゅうた整骨院のインスタグラムページはコチラ>
りゅうた整骨院公式Instagramページ
宝塚中山寺店 住所:兵庫県宝塚市中山寺1-9-13
(阪急中山駅徒歩3分)
TEL:0797-87-3105
宝塚逆瀬川店 住所:兵庫県宝塚市逆瀬川2-1-11
(阪急逆瀬川駅徒歩1分)
川西店 住所:兵庫県川西市多田桜木1丁目4-23 桜木イーストビル1階
(能勢電鉄鼓滝駅5分)
TEL:072-744-3325
2021年01月30日
80代 男性
歩行中、自動車に跳ねられ救急車に運ばれたが、運良く頚部捻挫、腰部捻挫、右膝関節捻挫、右脛の裂傷で済んだ。
しかし、上記の部位が痛み整形外科を受診したが、貼り薬等の処方だけで終わってしまった。
縁があり、りゅうた整骨院・鍼灸院に来院され、マッサージ・電気治療・運動療法を受けたところ、右の手で頭の後ろから左の耳が掴めなかったのが掴めるようになったことや、入浴中、背中を流す時、肩が痛かったのも軽減され、腰の痛みも軽減された。
しかしながら、生身と自動車の事故の為、事故以前は身体の不調が一切無かったのだが、痛みが出てきているため、毎日の治療を受けられている。
<りゅうた整骨院公式ホームページ>
宝塚市のりゅうた整骨院
<宝塚市の交通事故治療・むち打ち治療情報サイト>
宝塚市交通事故治療・むち打ち治療.com|整形外科連携の整骨院
<おかげ様で宝塚市口コミ上位!>
WEB上の患者様の口コミはコチラ
<鍼やお灸に関する口コミ上位!>
りゅうた整骨院公式しんきゅうコンパスページ
<りゅうた整骨院のフェイスブックページはコチラ>
りゅうた整骨院公式facebookページ
<りゅうた整骨院のインスタグラムページはコチラ>
りゅうた整骨院公式Instagramページ
宝塚中山寺店 住所:兵庫県宝塚市中山寺1-9-13
(阪急中山駅徒歩3分)
TEL:0797-87-3105
宝塚逆瀬川店 住所:兵庫県宝塚市逆瀬川2-1-11
(阪急逆瀬川駅徒歩1分)
TEL:0797-26-7758
川西店 住所:兵庫県川西市多田桜木1丁目4-23 桜木イーストビル1階
(能勢電鉄鼓滝駅5分)
TEL:072-744-3325
2021年01月30日
20代女性 西宮在住
一般道で信号待ちで停車中に追突事故。
バンパーとマフラーが凹む損傷。
事故の衝撃で、首・腰・手首の痛み、頭痛・吐き気などの症状を訴えて来院されました。
来院当初は筋緊張が強く、全体的に弱い刺激での施術でした。
約2ヶ月ほどで症状は緩和されましたが、定期的に出てくる頭痛と指の痛みに悩まされ、半年間来院されました。
施術開始から半年で症状は完治し、今は元気に過ごされています。
事故に遭うと、比較的小さな衝撃でも様々な症状が出ます。
停車中など力が抜けている瞬間に、体に衝撃が加わると、思いもよらない場所に痛みが出ることもあります。
当院では、この様な症状に対する施術以外にも、保険会社への対応や、慰謝料などに関してもサポートさせて頂きます。
<りゅうた整骨院公式ホームページ>
宝塚市のりゅうた整骨院
<宝塚市の交通事故治療・むち打ち治療情報サイト>
宝塚市交通事故治療・むち打ち治療.com|整形外科連携の整骨院
<おかげ様で宝塚市口コミ上位!>
WEB上の患者様の口コミはコチラ
<鍼やお灸に関する口コミ上位!>
りゅうた整骨院公式しんきゅうコンパスページ
<りゅうた整骨院のフェイスブックページはコチラ>
りゅうた整骨院公式facebookページ
<りゅうた整骨院のインスタグラムページはコチラ>
りゅうた整骨院公式Instagramページ
宝塚中山寺店 住所:兵庫県宝塚市中山寺1-9-13
(阪急中山駅徒歩3分)
TEL:0797-87-3105
宝塚逆瀬川店 住所:兵庫県宝塚市逆瀬川2-1-11
(阪急逆瀬川駅徒歩1分)
TEL:0797-26-7758
川西店 住所:兵庫県川西市多田桜木1丁目4-23 桜木イーストビル1階
(能勢電鉄鼓滝駅5分)
TEL:072-744-3325
2021年01月29日
40代男性 宝塚市在住
一般道で停車中に後方からの追突事故。
追突による衝撃で頚部捻挫・腰椎捻挫を誘発し、痛みを訴えて来院されました。
当初は『痛みが強く首が回らない』『腰を反らすと痛みが走る』など日常生活にも支障がでていましたが、3ヶ月が経過する頃には日常生活の中で強い痛みが出ることはほとんどなくなりました。
少し残る痛みと可動域の制限が取れるまでおよそ半年程かかりました。
事故後の体の痛みはなかなか治りにくかったり、最初はそれ程強くない痛みでも後から段々とツラくなることがあります。
どんなに軽微な事故だったとしても必ず病院で診察を受け、その後整骨院などで治療を受けてください。
事故に遭った時は早期に治療を受けることが大切です。
<りゅうた整骨院公式ホームページ>
宝塚市のりゅうた整骨院
<宝塚市の交通事故治療・むち打ち治療情報サイト>
宝塚市交通事故治療・むち打ち治療.com|整形外科連携の整骨院
<おかげ様で宝塚市口コミ上位!>
WEB上の患者様の口コミはコチラ
<鍼やお灸に関する口コミ上位!>
りゅうた整骨院公式しんきゅうコンパスページ
<りゅうた整骨院のフェイスブックページはコチラ>
りゅうた整骨院公式facebookページ
<りゅうた整骨院のインスタグラムページはコチラ>
りゅうた整骨院公式Instagramページ
宝塚中山寺店 住所:兵庫県宝塚市中山寺1-9-13
(阪急中山駅徒歩3分)
TEL:0797-87-3105
宝塚逆瀬川店 住所:兵庫県宝塚市逆瀬川2-1-11
(阪急逆瀬川駅徒歩1分)
TEL:0797-26-7758
川西店 住所:兵庫県川西市多田桜木1丁目4-23 桜木イーストビル1階
(能勢電鉄鼓滝駅5分)
TEL:072-744-3325
2021年01月28日
70代夫婦 宝塚市在住
交通事故によるむち打ち症、腰痛症
車を運転中、交差点で赤信号で停車していたところ後方より衝突。
事故件数で上位に挙がってくる「追突事故」です。
レントゲンで骨の異常はいられないものの、首、肩、腰に痛みが強く出ていた。
むち打ち症の疑いがあり、症状も重い感じでした。
最初は心のケアをしながら施術していきました。
1ヶ月半ほどで大きな症状が治まってきました。
施術期間は全部で3ヶ月でしたが、ほとんど症状が無くなるまで回復しました。
施術内容は徒手療法で頸部、腰部の筋肉を緩めMIインパクトやトムソンベットなどで骨格矯正を行っていきます。
加えて電気療法、温熱療法、運動療法を行っています。
その他にも保険会社への対応や慰謝料などに関してもサポートさせて頂きます。
<りゅうた整骨院公式ホームページ>
宝塚市のりゅうた整骨院
<宝塚市の交通事故治療・むち打ち治療情報サイト>
宝塚市交通事故治療・むち打ち治療.com|整形外科連携の整骨院
<おかげ様で宝塚市口コミ上位!>
WEB上の患者様の口コミはコチラ
<鍼やお灸に関する口コミ上位!>
りゅうた整骨院公式しんきゅうコンパスページ
<りゅうた整骨院のフェイスブックページはコチラ>
りゅうた整骨院公式facebookページ
<りゅうた整骨院のインスタグラムページはコチラ>
りゅうた整骨院公式Instagramページ
宝塚中山寺店 住所:兵庫県宝塚市中山寺1-9-13
(阪急中山駅徒歩3分)
TEL:0797-87-3105
宝塚逆瀬川店 住所:兵庫県宝塚市逆瀬川2-1-11
(阪急逆瀬川駅徒歩1分)
川西店 住所:兵庫県川西市多田桜木1丁目4-23 桜木イーストビル1階
(能勢電鉄鼓滝駅5分)
TEL:072-744-3325
2021年01月27日
交差点を右折中に後方車に追突された。
衝突時にシートベルトによって胸に大きな負荷がかかったことで肋間神経痛の様な症状が出現した。
受傷部位は頸部痛・腰部痛・胸部の痛みを訴えています。
診断ではむち打ち症・腰痛症・胸部痛でレントゲンによる検査では骨に異常は見られなかったが首・腰・肘に痛みが強く出ている。
施術内容は徒手療法により頸部・腰部・胸部の筋緊張緩和やMIインパクトによる関節可動域の向上。トムソンベットを使った骨格治療も、行っています。他にも電気治療、温熱治療、運動療法も取り入れながら治療にあたっています。
治療期間は今月で4ヶ月目になりますが全体の大きな痛みが取れ、後は動作時痛や圧痛などが少し残っている。
<りゅうた整骨院公式ホームページ>
宝塚市のりゅうた整骨院
<宝塚市の交通事故治療・むち打ち治療情報サイト>
宝塚市交通事故治療・むち打ち治療.com|整形外科連携の整骨院
<おかげ様で宝塚市口コミ1位!>
WEB上の患者様の口コミはコチラ
<りゅうた整骨院のフェイスブックページはコチラ>
りゅうた整骨院公式facebookページ
住所:兵庫県宝塚市中山寺1-9-13
(阪急中山駅徒歩3分)
TEL:0797-87-3105
宝塚逆瀬川店 住所:兵庫県宝塚市逆瀬川2-1-11
(阪急逆瀬川駅徒歩1分)
TEL:0797-26-7758
川西店 住所:兵庫県川西市多田桜木1丁目4−23桜木イーストビル1F
(能勢電鉄鼓滝駅徒歩5分)
TEL:072-744-3325
2021年01月27日
40代女性 宝塚市在住
交通事故によるむち打ち症、腰痛症
車を運転中、交差点手前で赤信号で停止しようとしたところ後方より衝突。
3台玉突きの先頭。
レントゲンで骨の異常はいられないものの、首、腰に痛みが強く出ている。
現在腰痛の体性反射でお腹に痛みが出現。
施術内容は徒手療法で腹部、頸部、腰部の筋肉を緩めmiインパクトという関節可動域を広げる機器を用いています。加えて電気療法、温熱療法、運動療法を行っている。
現在施術を初めて2週間、少しずつだが痛みが緩和してきている。
3ヶ月で治癒を目指している。
<りゅうた整骨院公式ホームページ>
宝塚市のりゅうた整骨院
<宝塚市の交通事故治療・むち打ち治療情報サイト>
宝塚市交通事故治療・むち打ち治療.com|整形外科連携の整骨院
<おかげ様で宝塚市口コミ上位!>
WEB上の患者様の口コミはコチラ
<鍼やお灸に関する口コミ上位!>
りゅうた整骨院公式しんきゅうコンパスページ
<りゅうた整骨院のフェイスブックページはコチラ>
りゅうた整骨院公式facebookページ
<りゅうた整骨院のインスタグラムページはコチラ>
りゅうた整骨院公式Instagramページ
宝塚中山寺店 住所:兵庫県宝塚市中山寺1-9-13
(阪急中山駅徒歩3分)
TEL:0797-87-3105
宝塚逆瀬川店 住所:兵庫県宝塚市逆瀬川2-1-11
(阪急逆瀬川駅徒歩1分)
川西店 住所:兵庫県川西市多田桜木1丁目4−23桜木イーストビル1F
(能勢電鉄鼓滝駅徒歩5分)
TEL:072-744-3325
2018年12月26日
交通事故にあった場合、自賠責保険は同乗者はもちろん、加害者の車に同乗していた場合も適用できます。
■同乗者は何名でも、自賠責保険適用可能です。
自賠責保険は交通事故にあった車に同乗していた人(家族も含む)も賠償の対象になります。
加害者の車に同乗していた場合も同じです。
加害者が被害者の損害を賠償しなければならないという原則があるので、
例えば「加害者が夫、被害者が妻」というケースでも、不法行為の要件を満たす限り、
夫婦間でも当然に損害賠償請求が成立し、これを行使することができます。
被害者たる配偶者(この場合は妻)に他人性が認められる場合には、
加害者たる配偶者(夫)の運行供用者責任に基づいて,
自賠法16条の直接請求権の行使も認められます。
また、友人などの同乗者が、飲酒等の危険運転を容認・助長して事故に遭い、
負傷した場合も、損害賠償が認められます。(=「無償同乗(好意同乗)」)
■「共同不法行為」・・・複数の自賠責保険への請求
加害車両が複数ある事故の場合、自賠責保険の補償限度額は加害車両の数に応じて増えます。
自賠責保険は車両ごとに付保されるものだからです。
例えば、2台の車の衝突事故で双方に過失がある場合に、
どちらかの車に同乗していて負傷した人は、
両方の車の自賠責保険が使えるので、請求できる限度額が2倍の240万円になります。
被害者はどちらに損害賠償を請求しても、双方に請求してもかまいません。
どちらがどれだけ負担するかは加害者側の問題(過失割合による)であり、
被害者はどちらにしても認められた額の賠償金を受け取る事ができます。
※限度額が増えるといっても、大きくなるのは「支払いの枠」であり、
あくまで現実に生じた損害しか支払われないことに変わりはありません。
2018年12月18日
自賠責保険は「仮渡金」制度というものがあります。
どのような制度かといいますと、交通事故の場合損害保険が確定して正式に保険金が出るまでに、
当面の生活費や治療費などの出費がかさみ、被害者の負担が大きくなる場合が少なくありません。
示談交渉中でも被害者が請求すれば一時金の前払いをしてもらえる、被害者救済のための仕組みなのです。
仮渡金の特徴は・・・
・加害者から損害賠償請求の支払いを受けていない場合に請求できます。
・請求は被害者からのみできます。その時、加害者の承諾は不要です。 また、請求は一回だけ可能となります。
・保険金が支払われる時には、即払いの仮渡金を控除した残額が支払われます。
・最終的な確定額より仮渡金の額が大きい場合には、差額を返金しなければなりません。
・加害者側に損害賠償責任がないと判断された場合は、返金が必要になります。
このように自賠責保険は仮払い制度がありますので、
お金が無くても自賠責保険を上手に使うことで治療を受けることが可能です。
つらいおもいをして、それを我慢するなんてことの無いようにしましょう。
りゅうた整骨院・鍼灸院でも交通事故の施術はしておりますのでお気軽にお問い合わせ下さい。